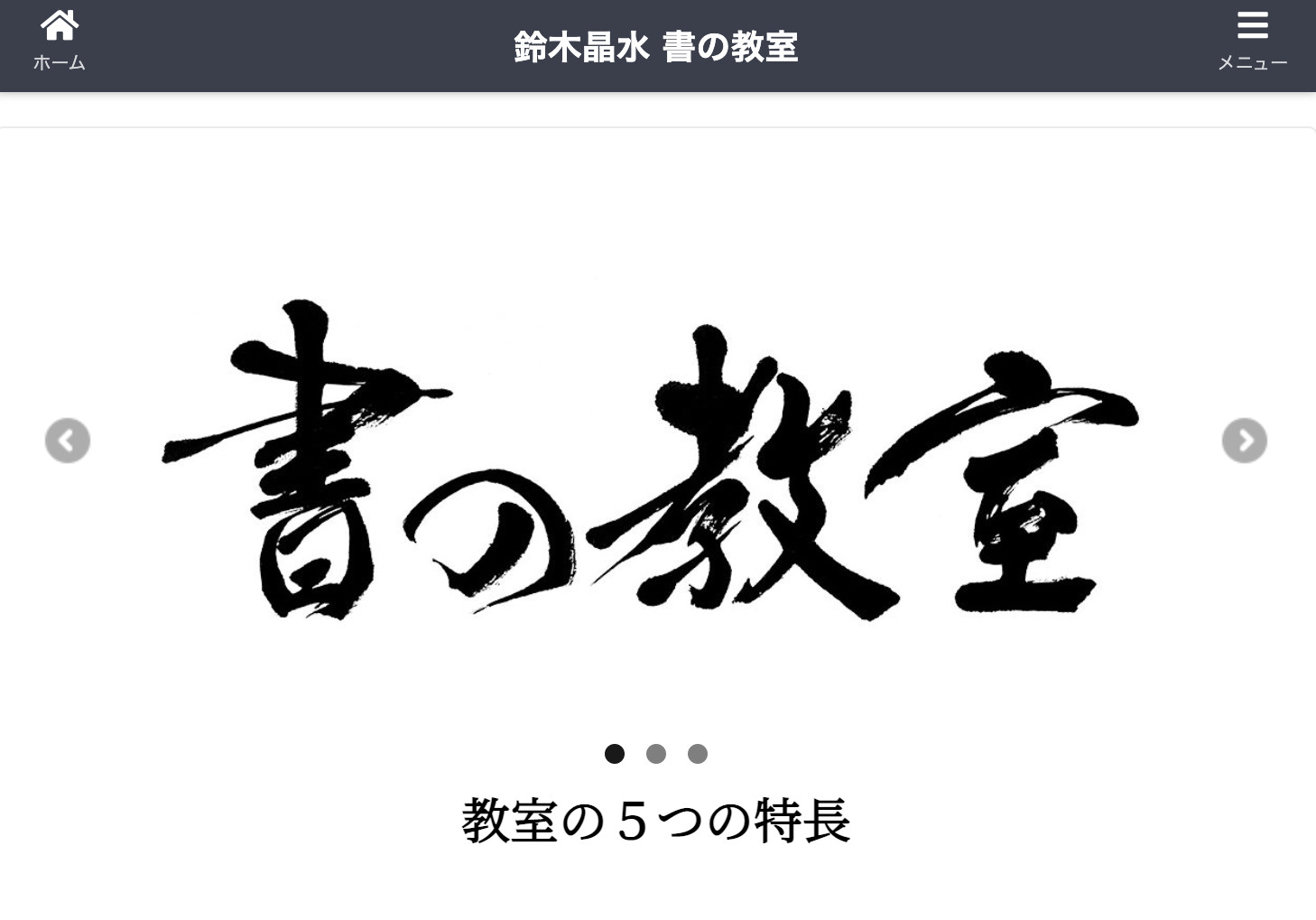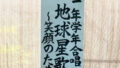子どもたちと向き合う日々は、楽しくやりがいのある一方で、悩みや葛藤も多く感じます。
書写の教室ですが、ただ淡々と字を教えるだけでは済まないのが現実です。
子どもたちからは、「やだ」「やりたくない」などの否定的な言葉や、「なんでやらなければいけないの?」などの問いかけが多かったり、行動に落ち着きがなかったりすることもあります。整理整頓や道具の扱いもまだ十分ではなく、一つひとつ丁寧に伝えていく必要もあります。
年齢が上がるにつれて、反抗的な態度やイライラした様子、不満、おしゃべり、ふざけることもあり、時には寝転ぶなど、集中力を保つのが難しい場面も増えてきます。
もちろん、落ち着いてきちんとふるまえるお子さんもいます。
この年齢でこんな立ち振る舞いができるのかと驚くことも多いです。
生徒さん一人ひとり、性格も環境も異なり、それぞれに合わせた対応が必要になります。
目指していることはたくさんありますが、限られた時間の中で全員にじっくり向き合うのは難しく、常にその子にとってより良い接し方を考えています。
子どもたちは裏表がありません。
大人が抑える感情や思いを、子どもたちは素直にストレートに表現してくれます。
小学校低学年くらいはまだ「自分と他人の違い」「社会的な視点」が未発達なため、「自分がやりたいこと=正しい」と感じやすいです。ルールより「今の気持ち」や「快・不快」を優先しやすいのも発達段階として自然なことです。
でも、これから成長するにつれ、これまで許されていたことが通用しなくなったり、社会の厳しさに直面することもあるでしょう。今まで自分が中心だった環境がそうではなくなっていきます。そんなときに自分の軸をしっかり保ち、柔軟に前向きに生きていける力を身につけてほしいと願っています。
たった週1度の短いお稽古時間ですが、書写と教室でのふれあいを通して、子どもたちがまっすぐに育っていくお手伝いができればと思っています。安心して過ごせる、信頼できる場、ほっとひと息つける時間であることも大切にしながら、書写にしっかり取り組むと同時に、国語力や算数力、そして小さな道徳も学べるような場所を目指しています。
短いお稽古時間でこんなに欲張って、当然思うようにいかないことも多いです。
私自身日々葛藤の連続です。
(今どき)「靴は揃えましょう」「正座をしてご挨拶」「鉛筆・筆の持ち方が良くない」「姿勢が悪い」「先生のお話を聞くときは手はお膝」「書いているときはお話しない」「あきらめない」「投げやりにならない」「物は投げない」「身の回りを片付ける」「筆は丁寧に扱う」「周りの子にちょっかいを出さない」「ドアの開け閉めは丁寧に」「寝転ばない」「一つ一つの動作を丁寧に」「良くない言葉は使わない」「ぶつぶつ文句ばかり言わない」「大きすぎる声は出さない」「単語だけで話さない」などなど、口うるさい先生だと思う子もいるかもしれませんが、朝のお経のように淡々と言い続けています。