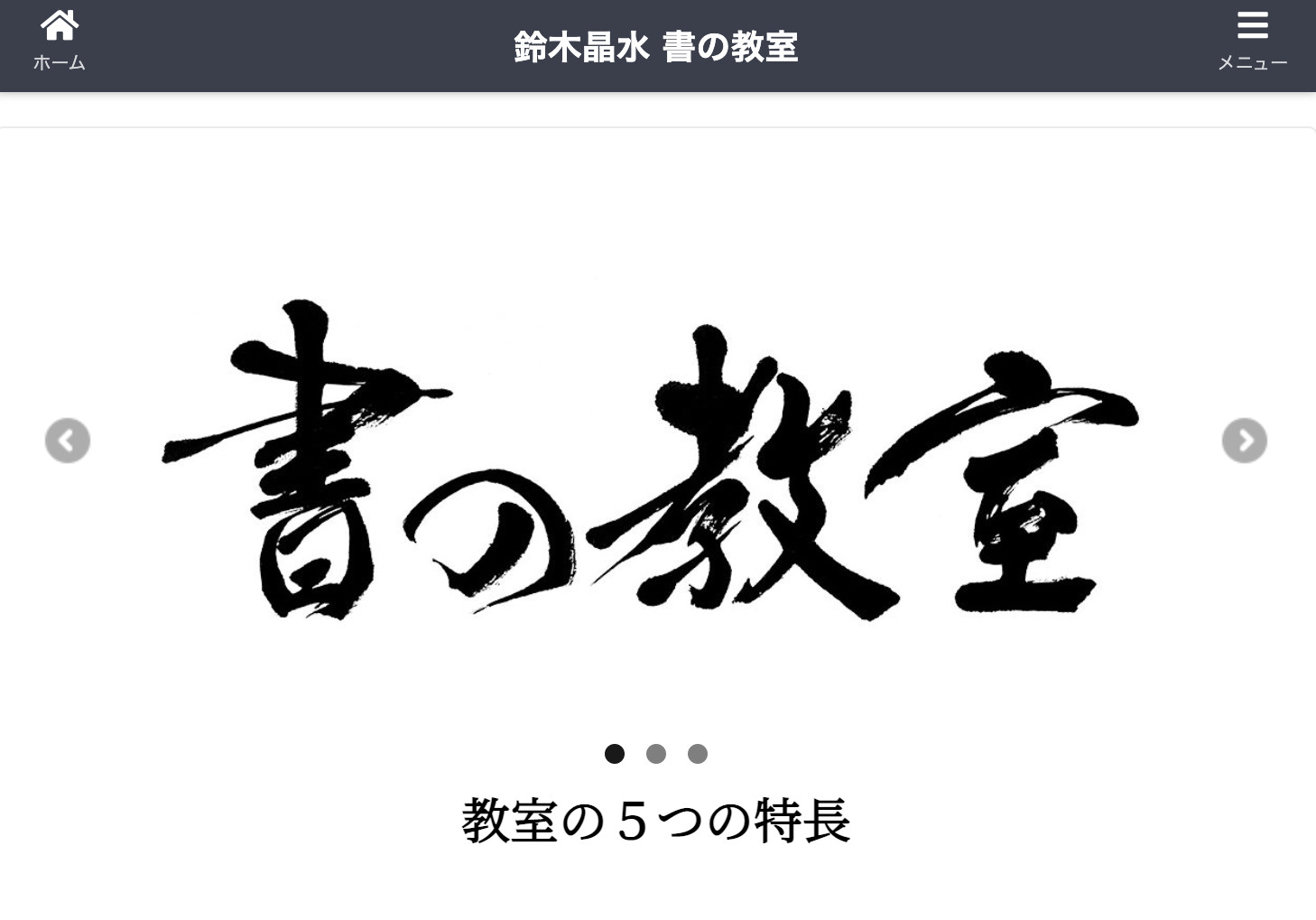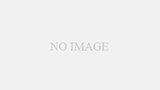最近、「勉強が嫌だ」と言う子どもや、自分の将来について悩む子どもを見かけることがあります。
ふと考えると、「勉強」という言葉自体が、なんだか強制的で苦しいもののようなイメージになってしまっているように思います。語源をたどると、「勉強」とはもともと、自分の力を高めるために励むこと。知識を覚えるだけでなく、考え方や思考の枠組みを理解し(概念)、本質を理解して応用できるようになるための行為なのです。だから、ここで言う「勉強」とは、「学び=できることを増やすこと」だと捉えてほしいと思います。
これからの時代、今まで人がしてきた仕事の多くは、ロボットやAIに置き換わっていくでしょう。すると、求められる能力はどんどん高度になり、単純作業や指示をこなすだけでは、社会に求められなくなるかもしれません。ここに不安を感じる人も多いのではないでしょうか。
でも何も、高度な能力を習得しなければならないというわけではありません。そんなことばかり求めていたら疲れてしまう人も居ると思います。勉強は「学校の教科」という狭い意味ではなく、教養や芸術、身体的な学びも含めた幅広い学びも同じように価値があります。どの学びも、考え方や思考の枠組みを理解し(概念)、本質を理解して応用できて初めて力になります。
私が思うのは、「できることを増やし、学びを掛け算していくこと」です。例えば、書道ができる人はたくさんいます。しかし、書道×ピアノ×スポーツ×お絵描き×料理などの好きなことや趣味、やったことがあることをすべて持っている人となるとごくわずかです。
この考え方は、確率で例えるとわかりやすいかもしれません。ひとつの学びを持つ人の割合が〇%、二つの学びを持つ人の割合が〇%×〇%…というように、掛け算するほど人数は減ります。つまり、多くの学びを掛け算した人ほど希少性が高くなり、個性や価値が生まれるのです。
だからこそ、子どもたちには「今できることを少しずつ増やす」という視点で学んでほしいと思います。ひとつのことを極めるのも素晴らしいですが、いくつもの学びを重ねていくことで、未来に選択肢と可能性を広げることができます。学びの掛け算は、人生の武器となり、未来への希望となるのです。