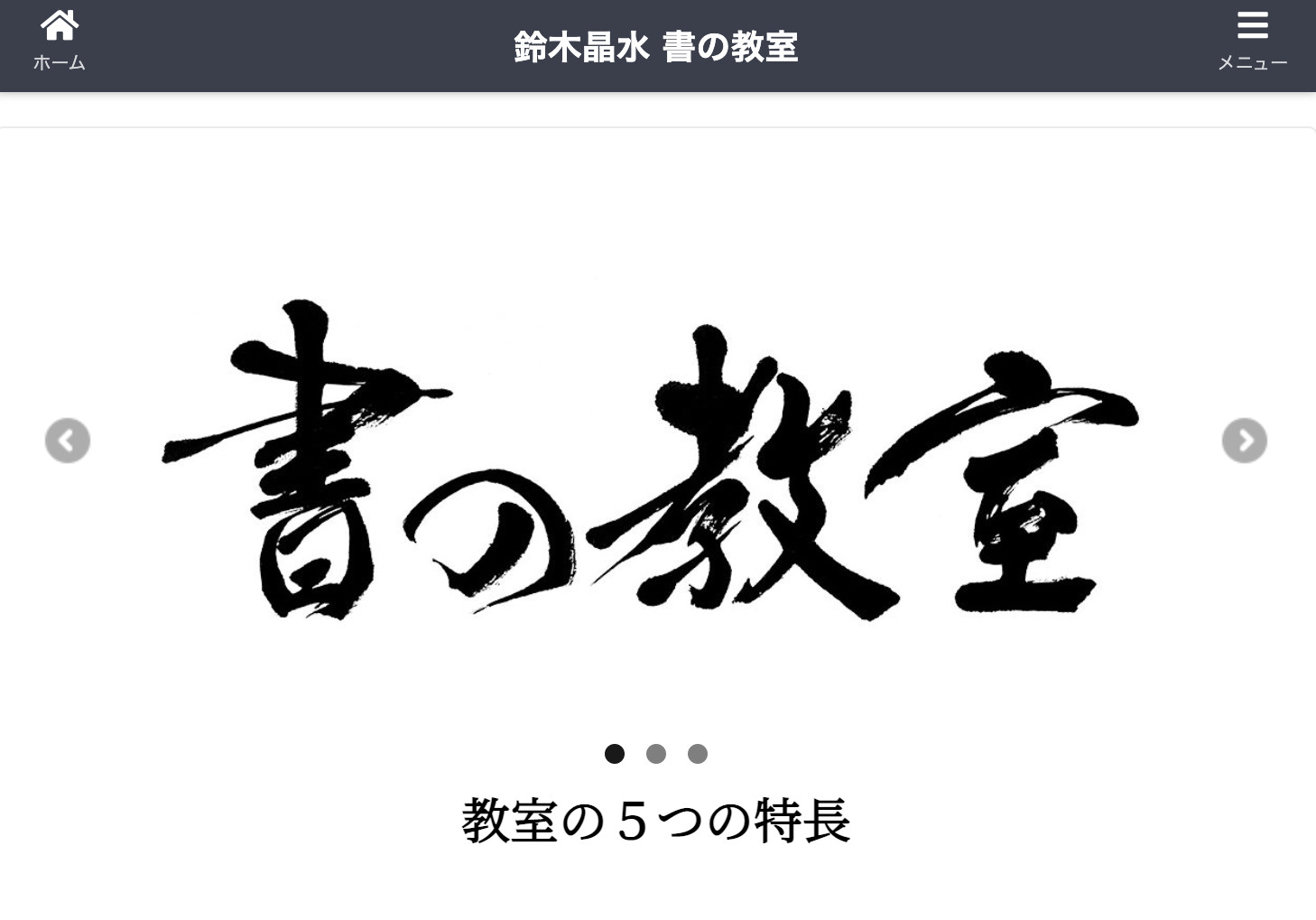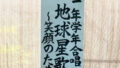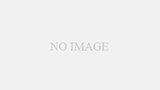時間の感覚と集中力について、ぼんやりと考えてみました。
時間の感覚というのは、脳への刺激や変化によって、早く感じたり、遅く感じたりします。
つまり、時間の感覚は文化や技術の進歩の速さに大きく影響されるのではないでしょうか。
現代はスマートフォンやAIの登場で作業が短時間で終わり、時間の流れもどんどん加速しているように感じます。
一方で、長時間じっくり集中する力や、自分で考える力は徐々に弱まっているように思います。
では、昔はどうだったのでしょうか。
たとえば縄文時代。
人々の生活は狩猟や採集、道具作りなどに多くの時間を費やしていました。
土器や集落の作り方も数百年単位で少しずつ変化する程度で、一生で体感できる変化はほんの数回しかなかったはずです。
時間はゆったりと流れ、長時間集中することが自然に行われていたと考えられます。
現代では、多くの情報をいつでもどこでも簡単に入手できるようになりました。
そのため、脳は常に活性化され、時間はあっという間に流れていきます。
その結果、短期集中型となり、集中力が持続しにくくなっているのではないでしょうか。
お教室でも、少し書くとすぐにお喋りをしたり、他のことに気を取られたりする子が多いように感じます。
しかし、お稽古を始めて脳が落ち着いてくると、静かに集中して取り組み始めます。(脳の活性化がなかなか収まらない子もいます)
また、読むこと自体を楽しむ読書は没入感を得やすいですが、情報を得るための長文を読むことを苦手とする人も増えているように感じます。
最近の若者がLINEなどで、言葉を省略したり、フレーズごとに区切って送る傾向も、その一例でしょう。
これからも技術の進歩と共に、時間の流れはさらに加速していくはずです。
技術の進化には多くのメリットがありますが、その一方で脳や体への負荷は増し、慢性的な疲労やストレス、注意力の分散、思考力の低下といった新たな危機が広がる可能性もあります。
だからこそ、意識的に「じっくり取り組む時間」を持つことが大切です。
書道や音楽、芸術、運動、読書など、時間をかけて没入できる体験は、失われつつある感覚や深い集中力を取り戻す手段となります。
心と体に必要な習慣や体験は、時代がどれだけ変わっても決して価値を失うことはありません。
むしろ今の時代だからこそ、意識して取り入れていきたいものです。