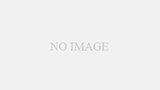日本習字の検定用紙は罫線がついています。
罫線がついている用紙で学習すると、罫線が無い用紙には書けなくなってしまうんじゃないの?というご意見もありますが、私の考えとしましては、罫線が入っている用紙で練習する方が効率的だと思っています。
字の練習をするときは、お手本を見て書くことが一般的ですが、お手本の字には多くの要素が詰まっています。
お手本を模写したりなぞる練習も良いですが、この方法だけで全ての字に応用させる力を身に付けるのにはとても時間と労力がかかります。
字は図形的な要素が強いと考えているので、まず罫線のある用紙で練習して外形や中心・構成・バランスの取り方を頭で理解しながら練習した方が効率も良く、応用も効くと思います。
また、指導者の「もっと長く」や「この角度」という表現は感覚的で、伝え方・伝わり方共に個人差が出てしまいます。罫線があることで、より正確に伝わるのではないかと思います。
他にも補助用具を使い、目指す姿をインプットさせる練習方法は多くあります。
(例)
スイミング→浮き輪、ビート板など
自転車→補助輪、三輪車、ストライダーなど
鉄棒(逆上がり)→補助ベルト、補助板
跳び箱→VRを使って飛んだ感覚を体験
昔は、ひたすら書いて「体で覚える」という練習が多かったと思いますが、現在は正しく整った字を書くためのメソッドもほぼ確立されていますし、学校教材の内容も変わってきています。忙しい現代では効率よく身に付ける方法を取るべきだと考えています。(書について深く学びたいと思えば、時間をかけて追及していけばいいのです。)
まず補助を利用して、中心はどこなのか、長さはどのくらいなのか、文字のバランスとはどういう事なのかなどを目で確認できる状態にしておきます。
「中心を揃えなさい」「もう少し長く」などという指導もありますが、私は子どもの頃から「そもそも中心てどこなの?」と思っていました。「中心は中心」「真ん中だよ」と言われても、いやそれはそうなんだけど・・・???といった感じで、自分の練習不足なのか、才能がないのか、感覚が低いのか、、、などと思っていました。
文字の中心はわかりやすい字もありますし、わかりにくい字もあります。
罫線が入った用紙で学習することで、字形とラインの関係が無意識に脳にインプットされます。
「まっすぐ」や「角度」のイメージも補助線があると曖昧になり難いです。
無意識に、と書きましたが勿論ぼんやり書いていればいいのではなく、意識することで無意識の領域に取り込む。これが「身に付ける」ということだと思います。
脳に映像としてインプットしていると、無意識に中心感覚が身に付き、いずれ罫線が無くても書けるようになります。

上の画像、BASICと読めますよね。
タイポグラフィの勉強もしたことがあるのですが、人の脳って既存の記憶から存在しない線を補填して見ることができるんですね。
ラインの感覚を身に付けるとあらゆる所で役立ちます。
もちろんずっと罫線ありの用紙を使うわけにもいかないので、徐々に罫線なしの用紙で練習していくことも必要です。